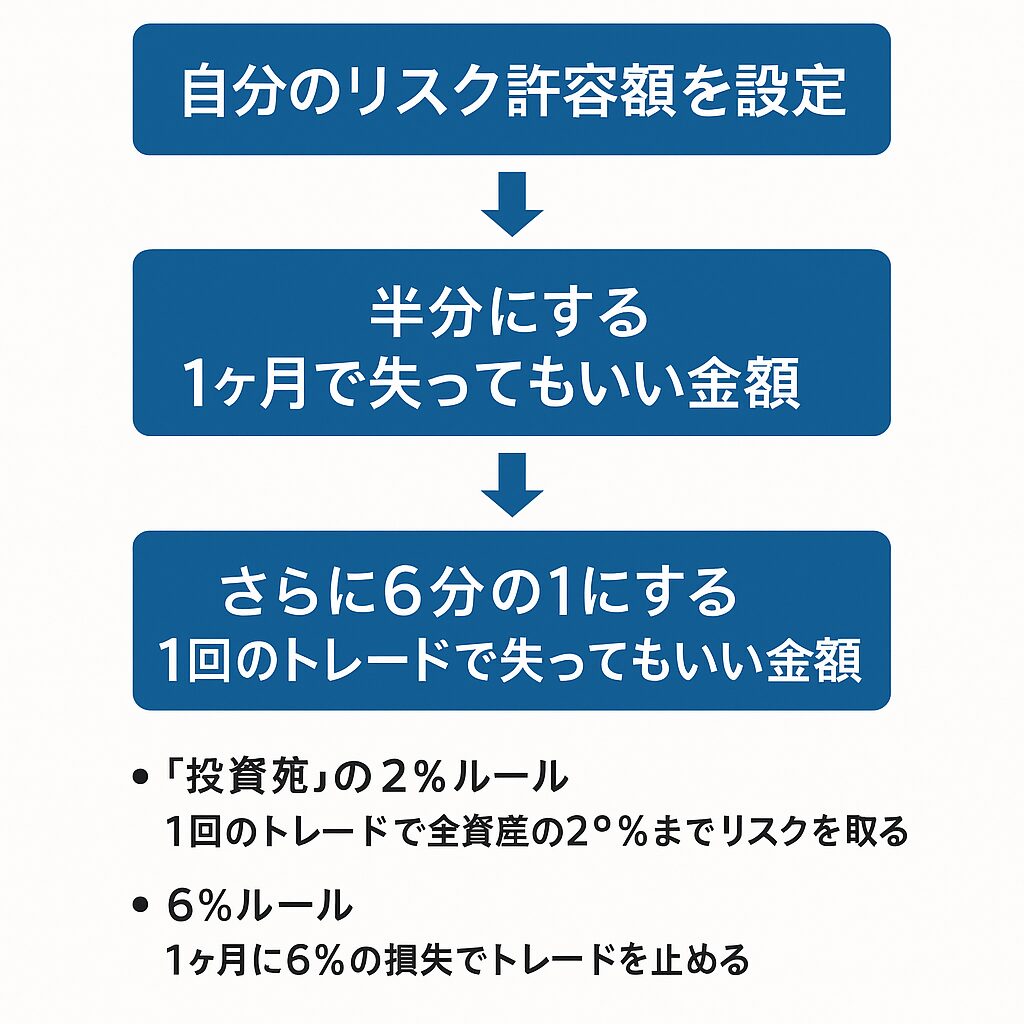💫はじめに
少し暑さが戻った東京。ただ何か秋の不安の感じる物語悲しさがあります。
📈 今日のマーケット / Market Highlights
2025年8月14日(木)の最新マーケット情報
日経平均:42,649.26円(前日比 −625.41円、−1.45%)
NYダウ(DIA):449.42ドル(前日比 +4.62ドル、+0.01%)
ドル円(USD/JPY):約147.38円(前日比 −約0.40円)
金価格(1540):14,855円(前日比 −145円、−0.97%)
日経平均は7営業日ぶりの反落となり、4万3000円を割り込みました 。ドル/円相場では、米国の利下げ期待と日本の金利上昇期待を背景に円高が進行しました 。 金価格は小幅に続落し、投資心理としてはリスク回避と市場の調整が交錯しているようです 。
🖥️今日のトピック
ベッセント発言が市場揺らす 日経平均625円安、日銀利上げ観測拡大:日本経済新聞
この記事の違和感は、財務大臣がFRB理事長職権の政策金利について発言し、それに対して市場が動いたということ。トランプ政権の性質を物語るものだろうか。GPTに調べてもらったところ、そうしたケースはこの10年ではあまりなかったらしい。
主な言及例とその背景
1. ジャネット・イエレン(財務長官:2021年〜2025年)
2025年1月15日:長期金利の高さを踏まえ、「より低い財政赤字」が必要だと言及しましたが、これは政策金利そのものへの直接的な発言ではありません。 2024年9月26日:財務市場の安定性の重要性について触れましたが、具体的な政策金利の目標や変更については述べられていません。
2. スコット・ベッセント財務長官(2025年就任)
現在(2025年8月)にかけて、複数回にわたり政策金利の大幅な引き下げを公に主張しています。 具体的には、「フェデラルファンド金利は1.5〜1.75ポイント低くあるべき」と述べ、9月には0.5ポイントのカットを開始するよう強く推奨しています。
これ以外には、政策金利について明確にコメントしたケースはほとんど確認できません。
ベッセント氏以前は、イエレン氏まで遡るというのですが、ハルシネーシヨンかな?
それ以前の財務長官の発言の確認をお願いしましたが、以下の回答。まあ、稀なんでしょうか。
主なケースと発言内容
ティモシー・ガイトナー(Timothy Geithner/在任:2009年~2013年)
債務上限に関して 2011年の債務上限問題では、ガイトナー長官は「上限を引き上げなければ米国の債務不履行(デフォルト)を引き起こす」と警告しました。このデフォルトによる影響は、借入金利の急上昇や金融市場の混乱を招く可能性があるとの認識でした。 ※重要なのは、政策金利そのものへの言及ではありませんが、財務政策と市場金利の関係を明確に意識していた点です。 利払いコストと経済への影響 2011年5月、ガイトナー長官は「借金の利払いが増えることは将来の税金や他の投資を犠牲にする」「政府債務が積み上がると、貸し手はより高い金利を要求するようになり、民間投資が抑制される」として、利息負担の経済への悪影響を強調しました。 こちらも政策金利そのものではなく、金利負担と財政運営の資金配分に関する発言です。 通貨政策・量的緩和に対する姿勢 量的緩和(QE)に関して、ガイトナー長官は「アメリカが意図的に通貨(ドル)を弱める政策をとることはない」と明言し、通貨安政策には否定的な立場を示しました。 ここでも直接的な政策金利のコメントではありません。
ジャック・ルー(Jacob J. Lew/在任:2013年~2017年)
経済・雇用の回復を重視 2013年5月、ルー長官は「景気回復の成果として経済が強くなっている」「雇用の回復・拡大が続いている」と述べ、成長戦略の一環として雇用創出を強調しました。 また、2015年の経済回復について述べた発言もあり、危機後の金融改革の成果を示しています。 政策金利への直接的な言及は見られません。
米国も多く変容しているのかもしれませんね。
✨最後に
マーケットのは、世界への目を見開かせる格好な学校です。付き合わないわけにはいかないですね。
それでは。